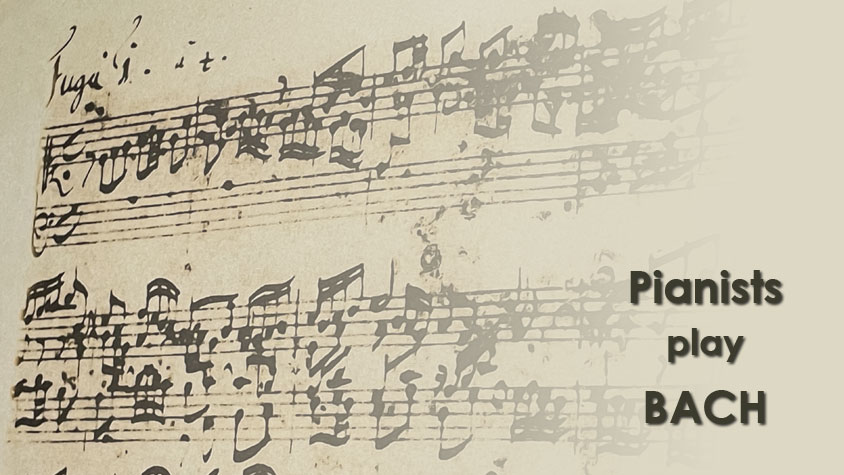こんにちは、たまにピアノでバッハを弾くこともある音響設計が専門の建築士・紅です。今回はJ.S.バッハの鍵盤楽曲をピアノで弾くピアニストとその音源を紹介していきたいと思います。
バッハの時代にはまだピアノが無かったので、バッハが残したピアノ曲というのは存在しませんが、当時の鍵盤楽器であるチェンバロ、オルガン、クラヴィコードのための作品は数多く存在し、しかも超名曲揃いです。
そして現代のピアニストたちは、そんな優れた鍵盤楽曲をピアノならではの表現、解釈で演奏し、たくさんの素晴らしい録音を残してきました。
バッハがピアノのために作ったものではない曲をピアノで弾くことの是非については、様々な意見があり、ここではあえて議論するつもりはありませんが、個人的には音楽を楽しむことができるのであれば全然アリだと思います。
いままで聴いてきたピアノによるバッハ演奏で、5人の好きなピアニストとその録音を挙げてみます。
アンドラーシュ・シフ Sir András Schiff
僕がバッハを聴くとき、そしてピアノを弾く上で参考にするとき、デフォルトとしているのはシフの録音です。
「現役最高のバッハ弾き」と謳われ、世界的に認められた存在と言ってよいでしょう。最近はすっかり巨匠の風格が板についてきました。ただ、20年近く昔の話ですが、当時所属していたアマチュアピアノサークルの仲間内ではそこまで注目されておらず、僕が一人で騒いでいたような記憶があります。
シフの弾くバッハは、一言でいうと「メリハリが効いている」ではないかと思います。アーティキュレーションが多彩で、スタッカート、テヌート、スラ―、レガートの弾き分けが巧みです。

漢字でいうところのトメ、ハネがくっきりしていると言いましょうか・・
溌剌とした躍動感や、なめらかで流麗な美しさなど、表現の幅、奥行きがとても広く、ある意味ピアノならではの自由な表現と言えるかもしれません。それでいて、チェンバロの奏法を意識した面もあります。
長調の曲にシフの特徴がよく表れているように思います。特に好きな録音は、フランス組曲5、6番、パルティータ1、4、5番、イタリア協奏曲、平均律1巻17番、シンフォニア5番、コンチェルト2、4番です。全部明るい曲ですね!



このうちフランス組曲6番、パルティータ1番、4番の序曲は弾いたことがあります。
以前、ピアノの友人が、シフの弾くパルティータ1番で、メヌエットIIを弾いたあとにもう一度メヌエットIを弾くところがあって、その戻る瞬間に入れているオリジナルの装飾音が「天使が下りてくるみたい」と言っていました。これがとても気に入り真似して弾いてみるのですが、どうしても上手く弾けません・・。
シフは自身の著書の中でもバッハの演奏について触れており、これが大変興味深いです。
シモーヌ・ディナースタイン Simone Dinnerstein
ジュリアード音楽院で学んだのち、目立ったコンクール入賞歴もないまま、結婚、出産と平凡な生活を送るなか、あるときカーネギー・ホールでのリサイタルを自主企画で開催し、このとき弾いた「ゴルトベルク変奏曲」が注目されました。そして同曲を収めたアルバムが発売されるとビルボードのクラシック・チャートで1位に。いまでは国際的に活躍するピアニストとなりました。
そんなアメリカンドリームのような経歴を持つディナースタインの弾くバッハは、確かに心に残る演奏だと思います。
ゴルトベルクと言えば、まっ先にグールドの強烈に個性的な演奏が挙がるわけですが、ディナースタインの演奏には刺激的な要素は少なく、麗らかな春の木漏れ日のような、心温まるものです。しかしながら本人はグールドの影響を強く受けていて、演奏の参考にしたとのこと。一見、対極的に感じられますが、確かに穏やかな雰囲気に流されるだけでなく、構成的にはしっかり作りこまれており、だから聴いていて飽きるようなことが無いのだと思います。また、だからこそ世界クラスのピアニストとして認められたのでしょう。
ディナースタインの弾くバッハで僕が一番好きなアルバムは『Something Almost Being Said』です。バッハのパルティータ1番と2番、シューベルトの有名な4つの即興曲が収められていて、この中のパルティータ1番がとても気に入りました。
シフの明るく溌剌とした演奏も良いですが、ディナースタインはしっとりととても丁寧に、そして優しい温もりがあり、聴いていてとても穏やかな気持ちになります。
このアルバムジャケットの内側には、ディナースタインの旦那様とお子さんと思われる、小さな子を抱く父親の姿がさりげなく映っていて、ほっこりさせてくれます。
ヴィキングル・オラフソン Víkingur Ólafsson
個性的なピアニストが世間に登場すると、そのたびに「グールドの再来」というキャッチコピーが付けられたりするわけですが、僕がまさにその通りだと思ったのはいまのところヴィキングル・オラフソンだけです。
オラフソンの『バッハ・カレイドスコープ』というアルバムを初めて聴いたとき、衝撃を受けました。もういい加減出尽くしたと思っていたバッハのピアノ表現で、まだこんな新しい解釈があったのかと、目から鱗でした。
個性的というと、好みがはっきり分かれるようなクセの強い演奏、あるいは大道芸的な派手なパフォーマンスといったイメージがあるかと思いますが、オラフソンの場合はそういったものではなく、あくまでも理知的でシャープ、非常にクールな演奏です。
そしてこれはバッハに限ったことではないですが、アルバムの作り方、選曲やその曲順が大変よく練られており、一曲ずつ取り出して聴くのではなく、アルバム全体の構成や流れを一つの大きな作品として楽しむように作られています。
『バッハ・カレイドスコープ』も、普通なら平均律、パルティータ、ゴルトベルクなど曲集ごとにアルバムにまとめるところをそうはせず、インヴェンションのようなポピュラーな曲の間に、あまり知られていないマニアックな曲や、バッハ自身あるいは後年の作曲家や演奏家、またオラフソンが編曲したものなどを織り交ぜ、文字通り万華鏡のようなアルバムに仕上がっています。
ピエール=ロラン・エマール Pierre-Laurent Aimard
イヴォンヌ・ロリオに師事し、メシアン国際コンクールで優勝。キャリアのスタートがブーレーズの元で現代音楽の演奏家ということから、バッハとは縁が遠いように思われますが、ベートーヴェンやリストの録音もあり、いまでは幅広いレパートリーを持っています。



僕が好きなピアニストの一人で、メシアンの20のまなざしやベートーヴェンのコンチェルトは名盤だと思います。過去には来日公演に赴き、サインをもらったりしました。
ドキュメンタリー映画『ピアノマニア』では、主役の調律師に難しい注文を付けまくるちょっと面倒くさいピアニストとして登場し、そのやりとりの面白さから、映画の製作当初はその予定ではなかったのに、最終的に準主役のような立ち位置になっています。そして、ここでキーとなる曲がバッハの「フーガの技法」です。
エマールがフーガの技法の録音に取り組む様子が、調律師の目線で語られており、この映画に描かれた過程で完成されたアルバムが下記の『バッハ:フーガの技法』なのです。映画を観てから聴くとより感動すること請け合いです。
フーガの技法はバッハ最晩年の未完の作品ですが、バッハの持てる技量を余すところなく注ぎ込んだ集大成でもあります。その普遍的な音楽に、僕はいつも宇宙を連想します。そしてエマールの弾くバッハは感情が一切削ぎ落され、楽譜に記された宇宙の音楽をただ忠実にピアノで再現しているのだと考えずにはいられません。
キース・ジャレット Keith Jarrett
言わずと知れたジャズの大家。ピアノを演奏しながら呻くので、グールドに通じるところがあるとも言えそうです。
しかし、ジャレットの弾くバッハはグールドとはまったく異なります。蒸留水のように無味無臭、不純物のようなものが一切排除された、端正でクセの無い演奏です。もちろんジャズを弾くときのような呻き声もありません。ジャズピアニストだから、自由奔放に即興やルバートがあるのだろうと思って聴くと肩透かしを喰らうかもしれません。
ピアニストがバッハを弾くとき、いかにほかと違うことをするか、どのようにして新しい解釈を織り交ぜるかと、あれこれ悩みぬいて創意工夫を盛り込むものですが、ふだんがジャズだと逆になるのでしょうか。
キース・ジャレットによる『平均律クラヴィーア曲集第1巻』は、ピアノ学習者がお手本としてもよいのではと思えるほどに基本に忠実で模範的。第2巻もありますが、こちらはピアノではなくチェンバロを弾いています。ほかにもゴルトベルクとフランス組曲もチェンバロで録音しており、どうやらバッハの演奏にはチェンバロの方が合っていると思ったようです。
さて、ここまで5人のピアニストを紹介してきましたが、もちろんほかにも著名なバッハ弾きはたくさんいます。
まずはここまで何度も登場したグレン・グールド。ピアノだけでなくその生活や言動も風変りな人物だったようで、クラシック音楽界の異端児的な存在ですね。バッハの演奏は極めて独特のものですが、熱狂的なファンも多く、特にゴルトベルクの録音は歴史的な名盤と言われています。ピアノ学習者がお手本とするにはほど遠い演奏スタイルですが、コアなファンは真似して演奏するのを楽しんでいるようです。
そのグールドが影響を受けたと言われるロザリン・テューレック。でもなぜかグールドの対極にあると言われたりして、それが僕がディナースタインのところで書いたことと重なり面白いです。ゆっくりと、堂々と、優美に歌い上げるバッハ。録音は古いですが、なんとも風格と味のある演奏です。
ロシアのバッハ弾き、タチアナ・ニコラーエワ。静謐で深みのある演奏は、まるで敬虔なキリスト教信者が神に祈りを捧げるような、そんな音楽です。平均律の録音が特に素晴らしく、1巻4番の重厚なフーガ、1巻12番の星降る夜の祈りのような静けさは聴きどころです。
現役では、マレイ・ペライアとアンジェラ・ヒューイット。前出の3人はバッハ弾きとして有名ですが、この2人はバッハ以外でも評価の高いピアニストです。ペライアは以前、サントリーホールでのリサイタルを聴いて大いに感動した経験があり、録音でもショパン・エチュードやヘンデル、スカルラッティは名盤です。ヒューイットのラヴェルも素晴らしいと思います。僕はまだこの2人のバッハの録音をあまり聴きこんでいないため、紹介できるような立場になく、いずれしっかり聴いてまたレビューしてみたいと思っています。